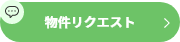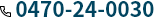「不動産コラム」の記事一覧(31件)
カテゴリ:不動産コラム / 投稿日付:2024/06/29 16:05
皆様は、新築やリフォームする際に、ポストで悩んでいますか?
どういう形にしようかな・・・?
どんな色にしようかな・・・?
ポストは必ず目に留まる場所に設置しますから
色々とこだわる方もいらっしゃると思います。
シンプルなデザインから、ディズニーとのコラボ商品まで
数多くのポストデザインがあります。
今多いのが、ポストと表札が一体型になった
「機能門柱」というものです。
こちらは今新しく建っている家でほとんどと言っていいほど
人気がある商品です。
過去のポストというのは、単独で壁につけたり、玄関横に置いたり
玄関と一体型になっている、いわゆるドアポストが主流でした。
しかし、防犯面が著しく低く、家の中が見えてしまったり
玄関のカギを開けられてしまったりと様々な被害がありました。
インターホンというものが存在していない時代では玄関まで来客がくるので
お子様がいるご家庭は不安要素にもなっていたのではないでしょうか。
平成からインターホンが普及し、玄関まで行かずとも来客が見えるものが
開発されてかなり減ってきました。
ちょっと重たい話になってしまいましたが、何が言いたいかというと
便利になり、インターネットも発達していく事で、
ポストとインターホンが合体した機能門柱が普及されて
尚且つ、デザインもかっこいい物から可愛い物まで
幅広くありますので、是非ご家族や、ご夫婦で検討してみてください!
細かな要望にもお応えできますので、弊社にもご相談ください!!
カテゴリ:不動産コラム / 投稿日付:2024/06/07 15:25
近年、古家を安く購入して自らDIYでリフォームをするという方が
増えてきている中で、自分自身で出来ない作業がいくつかあります。
その中の1つ、「浄化槽」という物を設置するのはかなり難題です。
古家であれば昔よく使われていた「汲取り便槽」が多く使われていました。
汲取り便槽とは何なのか?
一般的な呼び方であれば、ボットン便所と言われています。
いわゆるバキュームカーが便槽に溜まった汚物を回収するシステムです。
最近都会の方では、公共下水が主に導入されており、浄化槽を
使う地域は、南房総・館山、特に田舎に多い傾向です。
今回は、観点を南房総においてご説明していきます。
汲取り便槽から浄化槽に変えないといけないものなのかと言われると
変える必要は特にありません!
ただ、浄化槽に関しては汲取り便槽よりも性能も良く
1番のメリットは災害に強いというところです。
地震大国の日本では、全国で数多くの地震が発生しており
震度1程の地震も含めると1日に500回以上発生しています。
そんな地震大国だからこそ、地中に埋める浄化槽というのは
滅多に壊れないように設計されています。
その上、ボットン便所に比べて、臭いの発生も浄化されます。
設置費用で言えば、相場100万~150万円になり、金額だけ聞くと
諦めたい気持ちになりますよね。
ただ南房総市は、浄化槽設置に対する補助金があるのです!
しっかり専門業者に協力してもらえれば負担額が減るかもしれません!
そういった事も弊社は自社施工で行っており、少しでも
お客様の不安を解消するために尽力いたします!
ご相談だけでも構いません!是非お電話を!!
カテゴリ:不動産コラム / 投稿日付:2024/06/02 16:46
新築や改築する際、屋外コンセントが欲しいなと思う方いると思います。
屋外コンセントがあればとても便利ですよね。
家の中から電気を取れない状況でも屋外コンセントがあれば
困らないですし、照明なども付けたり多様性があります。
屋外での設置ですのでもちろん防水は必ずしましょう。
本体に防水カバーを付けるのが主流とされておりますが、
母屋との色の相性もあります。
ベージュやホワイトの外壁が多く、コンセントカバーは黒が多いので
対照的な色になってしまいがちです。
コンセントの為に外壁の色は変えられないので、工夫するには設置場所です。
あまり人目に付かない場所に設置するのがいいですが、そうなると
電気が使いたい時届かないなど、また同じ悩みに悩まされます。
なのでそういった細かな配色も気にしていくと綺麗に見えます。
後、1番気を付けた方がいいのは盗電です。
そんな人いるの!?と思う方が大半だと思います。
しかし実際、留守の間に携帯の充電をする為に勝手に使われていたと
過去の事例ではあるのです。
コンセントカバーでも盗電防止機能付きのカバーもあるので
道路沿いに家がある方や、人通りが少ないうえ敷地に容易に入れる方などは
導入した方が安全かと思われます。
室内からオン・オフできるものもあるので、機能があるコンセントを
使用するのがオススメです。
設置後のご相談や設置前のお悩みも弊社にご相談ください!
お客様に親身に寄り添ってお悩み改善します!!
是非お電話をお待ちしております!!
カテゴリ:不動産コラム / 投稿日付:2024/05/18 17:00
広い土地を購入して、新築で家を建てて残りの庭の部分は
どういう雰囲気にするか色んなバリエーションありますよね。
そこで、館山・南房総市ならではのエクステリアデザインをご紹介します。
皆さんは、館山・南房総と聞くと何を想像しますか?
「海産物」「自然豊かな街」など、、、
のどかな街並みを想像されると思います。
特に、千葉県の南房に行くにつれヤシの木が多く植えられています。
あのヤシの木って家に植えても大丈夫かな?
ハワイアンチックでオシャレだから植えたい!と
感じる方もいるのではないでしょうか。
それ、、家に植えても大丈夫です!!
そのヤシの木にも色んな種類があり住宅に向いている物もあるので
是非植えてみてはいかがでしょうか!
特にココスヤシ、カナリヤシは成長スピードも遅く
景観を損なったり、近隣に迷惑もかかりづらいです。
ワシントンヤシというのは、一般的に多く植えられていますが
かなり高く伸びるので要注意です。
ヤシの木は最初の1年間水やりをすれば、ほぼ管理いらず!
枯れた葉っぱなどを切ったり、成った実を処分するだけで保てます。
芝との相性も良く、根っこが干渉する事も極めて少ないです。
殺風景なお庭より、オシャレな外観を創ってみたいと思いませんか?
デザインから施工まで色んなご相談承っております!
気になる方は是非当社までお越しください!!
カテゴリ:不動産コラム / 投稿日付:2024/05/11 16:33
皆さんは、寝室の場所何階にありますか?
平家建てであれば、寝室を気にしなくていいのですが、
大体2階建てのお家が多いのではないでしょうか。
最近流行り多くなってきているのが2階リビングです。
1階部分に洋室、和室、ゲストルームを設けて主な居住スペースは
2階に設けるケースが増えてきました。
確かに2階にリビングがあると景観も良く日当たりも確保できるので
過ごしやすい空間になります。
ただそうなると1階に寝室があるという事になりますよね。
そのせいで睡眠不足になりうる事をご存じでしょうか?
大きく理由が3つあります。
まず1つ目は、2階の浴室、トイレや洗面所など、水回りが真上にあると
遅い時間に入浴するご家族や、夜勤帯の方などが使った時にかなり
排水の音が響きます。
特に木造住宅はマンションとかの造りに比べて音が大きいです。
なので使う時間帯も気を配らないといけないという事です。
そして2つ目は、もし寝室が道路側であったり、人通りの多い方にあったら
車の騒音、話声などが聞こえてやむを得ず二重窓を取り入れたり無駄なコストがかかります。
最後に3つ目は、特にツライ冬の時期です。
1階だと冬の時期の寝室はダイレクトに地面の冷えが感じられるので
冷え性の方もそうですが、寝つき寝起きの質が悪くなってしまいます。
日当たりを良くして暖を確保しようとしても、窓の大きさが大きくなるにつれ
窓からも暖気が逃げてしまう事もありますので、根本的に遮熱を施す必要があります。
そういった所も長く住むには気になりますよね。
「せっかく新しくしたのに住みにくいのは絶対避けたい!」
と、思っている方は是非弊社までご相談ください!
カテゴリ:不動産コラム / 投稿日付:2024/04/22 14:55
マイホームをリフォームしたい、新しく付けたいなどなど。
なるべく理想に近づきたいけど知識も何もないからどうしようと
悩んでいる方も、全部一気に覚えようとすると、かなり大変です!
まずは、どんな所を重要視するかが問題です。
例えば、昼間に陽の光を多く部屋に取り込みたいと思った時に
一番思いつくのは、「窓の増設」だと思います。
窓を多く付けたら中が丸見えになってしまったり、冷暖房が効きづらくなったり
色んな不安が出てくると思います。
確かに窓を多くすれば、陽の光は確保されたり、風通しが良くなったり
メリットもありますが、デメリットもあります。
窓が多い分、家具の置く場所が限られたり、色んな懸念点があります。
そういう時は、窓の位置を変えればいいんです!
太陽は日照中は基本、家の目線より上にある事がほとんどです。
窓の位置を上にすれば採光を確保しつつ、家具の置き場所を考えなくて済む
という事に繋がってきます。
窓の形や、大きさなども工夫すれば気になる事も減ってきます。
さて、その窓ですがしっかり性能を見ないと生活が過酷になります。
費用を抑えたいからと言って安い窓を買うと、夏・冬はかなり厳しい生活になります。
性能の中で「断熱性」はとても重要です。
オススメなのが、【Low-E複層ガラス】が高機能です!
夏は、太陽の熱を室内に通しにくく、冬は部屋の中の暖気を逃がしにくいのが特徴です。
全部同じ素材に変えるとなると莫大な費用になりかねませんので
寝室や、子供部屋など使用する場所を特定してそこだけ導入するのも
ひと工夫になり、コストを抑えられます。
このように身近な不安や、将来的な不安要素も解消します!
是非、マイホームのリフォームや新設したい時は弊社まで
ご連絡ください!お待ちしております!!
カテゴリ:不動産コラム / 投稿日付:2024/03/23 16:43
フェンスなどの工事をする際、皆さんはどういった基準で決めますか?
大きく分けると4つほどあるのではないでしょうか?
まずは、「デザイン」。
外構とはいえ、フェンスというものは敷地の一番外側。
敷地の境界線際に設置すると思います。
ですので、目にも止まりやすい分デザイン性が必要になります。
なので、家と外構の一体感を気にされる方は特にデザインを意識するでしょう。
その次は、「価格」です。
フェンスは、相当な数の品数があり、シンプルなものは安く
オシャレなものは、価格が高いイメージがあると思います。
しかし、比べてみると意外と金額の差というものはあまり無いです。
ですが、元々の金額が低いわけではないので、しっかりとカタログを見て
見積りを出して比べてみるのが良いかと思われます。
次に、「目透かし率」です。
目透かし率とは何かというと、例えばフェンスの梁の隙間が大きいと開放感が生まれ
敷地を広く見せながらでも、フェンスとしての役目があります。
隙間がなければ、開放感は減りますが、目線の防止、プライベート感が増したりと
人によって好みが変わってきますので、そこも重視される方多いと思います。
次に「通風率」です。
通風率とは、目透かし率と関係していて、やはり何もないところに
フェンスが立ってしまうと、当然風を受ける対象になります。
隙間が多い分、風から受ける衝撃はかなり和らぎます。
しかしそこが目透かし率と関係していて、目線の遮断を重視するか
風通しが良い方がいいのか、その部分も気になりますよね。
実際に、日本は台風が多い国と言われているので、夏になれば
連続で台風や、強風など災害があちこちで起きています。
フェンスも隙間が狭いと風の影響を受けやすくなるので、ちょっとした強風でも
壊れたりしてしまう恐れがあります。
なので、選ぶ時は、この4つの項目を意識しながら、地域性や立地を
加味して理想のフェンスを立てていければ、理想のマイホームの完成です。
そんなお悩みも、まとめて解消できるのが【自社施工】です!
実務経験豊富な社員が、寄り添います!是非お電話を!!
カテゴリ:不動産コラム / 投稿日付:2024/03/17 15:04
今回は、外構の中でも最近流行りだしている
「ドッグラン」についてご紹介していきます。
ドッグランを一から作るとなるとかなりの大工事になります。
ワンちゃんの好みに合った地面にしたり、遊具やフェンス
逃げ出さない様に細かなところを気を付けないといけません。
今回は、芝を張ったドッグランに視点を当てていきましょう。
まず芝生はどんなものを選ぶべきか。
天然芝なのか、人工芝なのか、選ぶものは自由です。
天然であれば、本物の芝生ですので、成長します。
なので、定期的な手入れが必要とされます。
その面、人工芝はその名の通り人工的に作られたものなので
伸びる事はないですが、材質が天然に比べても硬いです。
ご自分の生活リズムに合った芝生を選ぶことをお勧めします。
天然芝生で手入れしやすい芝生が「高麗芝」という種類です。
これは他の芝よりも手入れが簡単で、ゴルフ場などで主に用いられます。
特徴は、耐暑性・耐陰性・耐塩性・耐乾性・耐踏圧性は高いですので
万能的な芝です。
その反面、寒さに弱く擦り切れてしまうと回復が遅い傾向があります。
1平米あたりの金額も2,000円~3,500円程度で購入できます。
反対に人工芝は、天然芝より耐久性が高く、メンテナンスも必要ない。
どこでも簡単に敷く事が出来るのが特徴です。
ただ、初期費用が高く、経年劣化で寝てしまったり、抜けてしまうことも。
一番ネックなのが、火気厳禁という事です。
やはり夏などにBBQや花火をしながら、ワンちゃんも走り回れたら理想ですよね。
人工芝だと引火性が高いので、火事の恐れがあります。
芝生は面倒くさいからいいと思っても、土のままであれば
ワンちゃんの足が汚れてしまう、雑草が生えてきてしまう、意外と
何もしない事の方が少ない気がしますよね。
なので、ワンちゃんの為にも過ごしやすいドッグランを
作り上げていきませんか?
是非ご相談だけでもお問合せ下さい!!
カテゴリ:不動産コラム / 投稿日付:2024/03/08 16:26
新築の家や、新たにウッドデッキを設置する際に、何を意識しますか?
特に部材選びはとても悩むのではないでしょうか。
実際に、ウッドデッキを作るにあたって、どんなものが必要なのか
重要なものをいくつか例として挙げてみましょう。
まず1つ目は、ウッドデッキの中心になる木材です。
2つ目は土台となる基礎です。
3つ目は、部材同士の繋ぎとなる金物や、備品関係です。
今、簡単に3つの例を挙げていきましたが、この3つは
特に重要なものですので、適当に選ばない様にしましょう。
ただ木材を業者に発注すると、意外と高額であったり
業界用語で、理解しにくい部分も出てくると思います。
そういう時は、2×4木材(ツーバイフォー)の材料が
一番使いやすく、ホームセンターにも大体置いてあります!
土台となる基礎を選ぶ際には、まずウッドデッキの支柱を決めて
その大きさが合う、「独立基礎」というものを用意しましょう。
こちらは、コンクリート製品の土台になります。
形もさまざまで、台形の基礎が負荷に強いとされています。
最後に、繋ぎとなる接続金具や、ビス等です。
ウッドデッキは基本的に屋外に設置しますので、
雨ざらしになり、特に錆びやすいので、その分劣化も早い傾向です。
ですが、錆びにくいビスや、ステンレス製の接続金具もありますので
有効活用する事で長持ちさせることができます。
こういったウッドデッキを設立する場合も色んな事に
気を付けなければいけないことが分かったと思います。
そんな小さな悩みや、疑問があれば弊社にお問合せ下さい!!
カテゴリ:不動産コラム / 投稿日付:2024/02/25 11:14
皆さんは、ご自身の家の外壁は何色にしていますか?
清潔感もあって見た目もいい色と言えば、「ホワイト」「ベージュ」
大体この色が思い浮かぶと思います。
最近では、外壁を黒にする方も増えてきています。
黒にするメリットと言えば、外壁の汚れが目立たないのが黒の特徴です。
確かに外壁が黒色だと見た目もカッコよく存在感もありますよね。
ホワイトやベージュといった明るい色は、時が経つにつれ汚れも目立ちます。
外壁を少しでも長く綺麗に傷まなくする方法があるんです。
それは何かというと「屋根」です。
 | 近年流行りだしているのが、 「軒ゼロ住宅」という形状の家です。 |
それは何かというと、見た目だけで言うと屋根がありません。
屋根がないわけではないですが、皆さんが想像しているあの屋根ではないです。
雨水などはしっかり流れるようにはなっています。
 | 先程説明をした軒ゼロ住宅は、 屋根が外壁より飛び出していない分 雨水が直接、外壁を伝ってしまう為、 外壁の劣化が早い傾向があります。 |
なので、外壁を少しでも長く状態を維持するためには、
流行りを気にせず、屋根を作ることはとても大事なことです。
壊れてしまったり、ヒビが入ってしまっても軒ゼロ住宅と同じようになってしまうので
必ず、メンテナンスはこまめに行っていきましょう。
困ったときは、リフォームに力を入れている弊社にまずお電話を!!